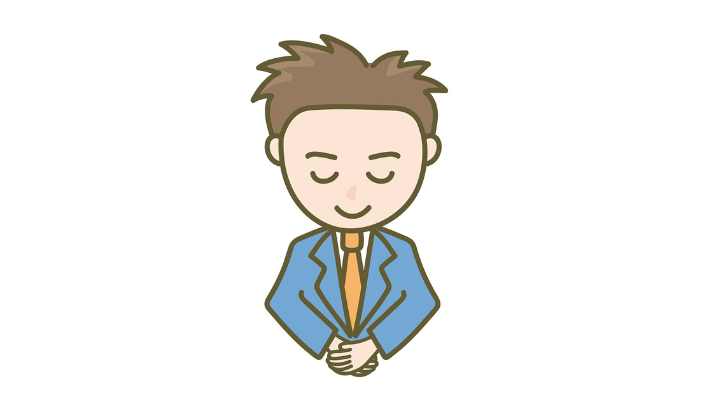2025/10/31
・表示数 7(この日の)
・訪問者 6人(同上)
・訪問者数 269人(この一か月間で)
【広告】ここをクリック→疲れた、でも本は読みたい。そんな時はAmazonオーディブル。本は、聴こう。
ごあいさつ
こんにちは、なにわt4eです。いつも本ブログをお読みくださり、本当にありがとうございます。読者さんご来訪ありの連続日数記録を順調に更新中です! 10/31時点で連続261日。ということは、あと104日で丸々1年を達成できるわけです。目指せ連続1年!
とは申しましても、そのためには何より「この本おもしろそうだな、読んでみよう」と思っていただける記事を書かなくちゃいけません。そもそも、それを目指して立ち上げたブログですからね。
今後も楽しくてお役に立てる記事を書いてまいりますので、よろしくお願いいたします。
現在、人気記事四天王のラインナップは以下の通り。
・『レディ・ジョーカー』(髙村薫)人間とは?組織とは?
・『ある行旅死亡人の物語』(武田惇志・伊藤亜衣)名もない女性が残した「物語」
・『ここは今から倫理です』第7巻(雨瀬シオリ)なんで殺しちゃいけないの?
・『デビルマン』(永井豪)「地獄へおちろ人間ども!」
安定のラインナップ、とりわけ『レディ・ジョーカー』『ある行旅死亡人の物語』の人気ぶりが不動です。
ちょっと気になっているのが『デビルマン』。人間の醜さや群集心理のおぞましさを抉り出した作品であるだけに、今も時々起きている炎上騒ぎとの関連で考えずにいられません。元々ファンの多い作品ですが、最近はそういう観点でお読みの方も多いかもしれませんね。
『ここは今から倫理です』は特に7巻をご紹介した記事がよく読まれるのですが、やはり「なんで殺しちゃいけないの?」という人類史上有数の難問に真正面から、それも高校生の視点から取り組んだ点に関心が集まっているのでしょうか? 私もそんな点がおもしろいと思っているわけですが。
他には塩田武士『踊りつかれて』『存在のすべてを』の紹介記事もじわじわ読まれています。人間のあさましさや社会の歪みもきちんと直視して、それでも人間を信じようとする塩田氏の作品は静かですが力強い。そこに惹かれる方が多いんでしょうね。私もその一人です。
成長日記20回目に至るまで
成長日記第19回と今回の間に上げた記事は以下の通りです。(全て本ブログの紹介記事へ飛びます)
・『拳奴死闘伝セスタス』第9巻(技来静也)「見たかッ!!! この野郎オォオ」
・『神々は渇く』(アナトール・フランス)「神々はその食欲によってこそそれとわかるものだからだ」
白熱の拳闘試合と重厚な人間ドラマをたまにユーモアも交えて描く『拳奴死闘伝セスタス』の第9巻、メインの見どころはエムデンの雄叫びですが、個人的に一番好きなのはミロンの成長だったりします。それを導いたのが、もっとも本人は導いたつもりないでしょうけど、ド偏屈のエムデンである点もおもしろい。これだから『セスタス』シリーズは読むのをやめられないのです。
『神々は渇く』本ブログ初、フランス文学のご紹介でした。「狂信の危うさ・世論の移ろいやすさ」というテーマが『踊りつかれて』と共通しているということと、現代日本においてとても切実なテーマだからという理由でご紹介しました。何よりブロトカッコいい。記事では触れませんでしたがエヴァリストの恋人エロディも信念というより恋愛的な意味でたくましい人物ですし、ブロトと度々論戦する神父ロングマールも、狂信的な人物ではありません。ブロトがアテナイスを保護するのに協力したり、ブロトが自分は利己主義的なだけだと言うのに対してそう自分を悪く言わないで下さいと言ったり、人間味豊かな人物です。
最近読んだもの
『ミヒャエル・コールハース/チリの地震 他一篇』ハインリッヒ・フォン・クライスト
陰惨かつ緊張感の高い作風で、知る人ぞ知る人です。ゲーテやシラーといった古典派と、その後のノヴァーリスに代表されるロマン派に挟まったような、独特な位置づけの作家。全てを投げうって理不尽と戦うミヒャエル・コールハースの姿は、案外現代の日本で共感されるのでは? 他の本に目移りしちゃって中断してますが、そっちが一区切りついたら改めて読みたいです。
【広告】ここをクリック→こちらから書籍情報をごらんください。
【広告】ここをクリック→こちらから書籍情報をごらんください。(kindle版)
『地球上の中華料理店をめぐる冒険』関卓中(チョック・クワン)
これがその目移り先の本。著者は映画監督らしく、映画のために世界各地の中華料理店をめぐり歩いて、その産物がこの一冊。まだ読んでる途中ですが、様々な波乱万丈の人生と人の思いがうかがわれてとってもおもしろいです。本ブログでご紹介するかどうかは未定ですが、ここではこの一節をご紹介します。著者がマダガスカルを訪れる第7章の末尾です。
校庭の生徒たちを見ていて、ほかの国々もこういう方向に向かうべきだと思えてならない。文化や人種がすっかり混ざり合い、先祖がどこの出身かはたいしたことではない状況である。本当に大切なのは、自分が故郷と呼べる場所で、自分のために築いた生活なのだ。(P.185)
なおP.256に「カシーノ・チョン・ワー(中華総会館)」という建物が登場するのですが、思わず「チャン・ワー」とつぶやいてしまった……。
【広告】ここをクリック→こちらから書籍情報をごらんください。
【広告】ここをクリック→こちらから書籍情報をごらんください。(kindle版)
次の記事もどうぞお楽しみに。
【広告】ここをクリック→疲れた、でも本は読みたい。そんな時はAmazonオーディブル。本は、聴こう。