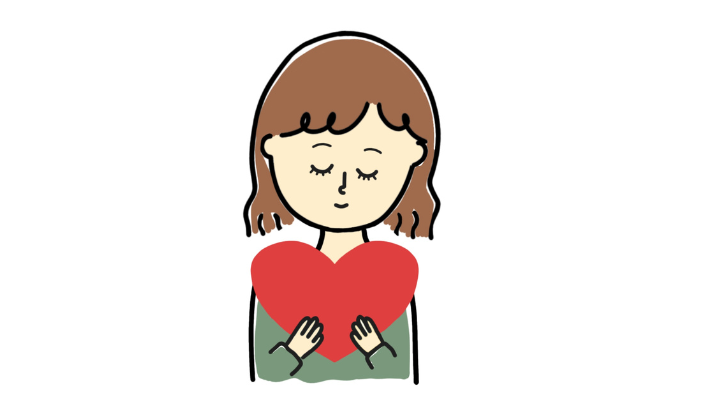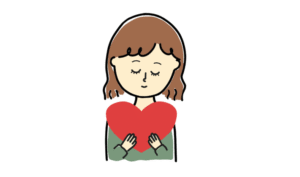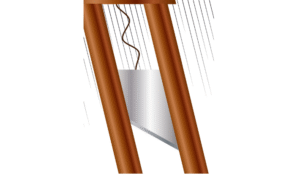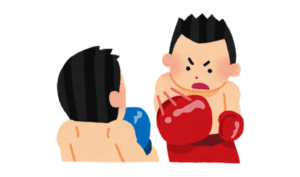先にまとめから~今こそ触れてください、優しく深いまなざし~
「人間の価値って、ホントに生産性だけで決まるの?」
「自分の死も、大切な人の死も、どうしてこんなに怖いんだろう?」
「自分たちだけ幸せになろうって考え方、結局ムリがあるのかな?」
あなたはそんなことを考えたことがありますか? 「ある」とお答えになったあなたにお尋ねします。
神谷美恵子さんをご存知ですか?
神谷美恵子さんは精神科医として、ハンセン病療養園の園長として、作家ヴァージニア・ウルフの研究者として、さまざまな活躍をされた方です。ですがいっこうに自分を誇ることはなく、自己卑下に近いくらい謙虚。また、本質的には行動より沈思黙考の方だったようで、著作や日記にはとても深く人間を見つめるまなざしがあります。
そんな神谷美恵子さんの著作、『人間を見つめて』が文庫化されました。
「本書を読めばあなたの疑問が解決します!」とは申しません。ただ本書は、あなたがご自分なりの答えを見つける手がかりをくれるでしょう。そしてきっと、「自分も周りの人たちも、もう少し大切にしよう」と思えるでしょう。
深い心と豊かな学識で静かに語りかけてくる神谷美恵子さんの言葉に、あなたが一緒に耳を傾けてくだされば、こんなにうれしいことはありません。
※本書は2004年にみすず書房からハードカヴァーで出版されていますが、この記事ではそこから「Ⅰ 人間について」のみを収録した河出文庫版に基づいてご紹介します。ご了承ください。
【広告】ここをクリック→こちらから書籍情報をごらんください。
【広告】ここをクリック→こちらから書籍情報をごらんください。(kindle版)
【広告】ここをクリック→疲れてる、でも本は読みたい。そんな時はAmazonオーディブル。本は、聴こう。
美濃達夫さんとの会話
「なにわt4eさん、神谷美恵子さんという作家…いや作家じゃないかな、ともかくご存知ですか?」
神谷美恵子さん!? 知ってるも何も、二十年来愛読してますよ。とりわけ、発達心理学を土台に人の一生を考察した『こころの旅』(←Amazonの紹介ページへ飛びます)にはどれだけ励まされたか。
「よほど愛読されてるんですね。それでは『人間をみつめて』はお読みになりましたか?」
ええ。これは未読だったんですが最近文庫になったので、いい機会だと思って読みました。
「取引先の方も読まれたそうで、先日おすすめされました。その方がおすすめしてこられるなんて珍しいので読んでみようとは思うんですが、大まかなところをお聞かせいただけますか?」
ええ、喜んで。
第一章 いのちとこころ
本書は三章からなっています。まず第一章は生命と精神、主に肉体をつかさどる「古い脳」と主に精神や理性をつかさどる「新しい脳」の関係を考察しています。
ここで神谷氏は、人間にとって生きることは「古い脳」と「新しい脳」の葛藤によって難しくなったと述べて、その原因を5つ挙げています。詳しくお話しすると長くなってしまうのですが、私の理解ですごく大ざっぱに申しますとこんな感じです。
1.本能と理性がケンカする
2.自分の自我と他人の自我がケンカする
3.自問自答して悩む
4.過去を悔いたり未来を不安に思ったりして悩む
5.「老い」「罪」「死」など宗教的・哲学的なことで悩む
「確かにそれだけあれば生きるのも大変だよな、という気はしますが、それらが人間らしさとか人間くささだという面もあるのでは?」
そうかもしれませんね。神谷氏の文章にもそうしたところへの優しいまなざしが端々に表れています。例えば
罪、病、老、死など、昔から宗教や哲学のテーマとなってきたことがらである。人間と生れて、こうしたことがらにぶつからないで済む人はまずないであろう。(P.29)
自分のあたまで、こうした「実存的」な問題を解決する方法がみつからなくても、少なくとも、そういうことを悩み考えることは、もっとも人間らしいことであり、生きることの重さを知りうるのも、こうした時だと思う。(P.30)
というように。
この章で、神谷氏はこんなことも書いています。
もし、人間のこころの働きを、知・情・意と分けるなら、広い意味での知性、あるいは「知恵」とは、情と意をも総合した創造的なものであろうと考えられる。これはコンピューターでは果しえない機能ではなかろうか。(P.38)
「近年のAIを思い出しますね」
美濃さんもそう思われますか? さすがに神谷氏がAIの存在を予見したわけではないでしょうけど、AIでは果しえない「知恵」とは何かを考えること、そしてそれを大切に育てること。これが今後の人類に求められることのような気がするんです。単に「AIに仕事を奪われないため」というだけでなく、「いかにも人間みたいに見えるAIがある現代に、人間が人間らしく生きるため」に。
他にも知的・身体障害のある方を振り返りつつ人格について考察する箇所、知性の養い方やあるべき使い方を考察する箇所などもあるのですが、全てに触れるととても長くなるので以下の文章を引用するにとどめます。
いうまでもなく、人間の思考能力には越えられない限界がある。それはアインシュタインすらわきまえていた。人類の前途は決して楽観できるとは思われない。「考える葦」は結局、悲劇的存在なのかもしれない。ことにその最大の武器である「考える力」を、ついには自らの首をしめるような方向に用いる可能性がまったくないとはだれがいえよう。
どうしたらこの悲劇を避け、地球上で人類が平和共存して行くことができるだろうか。このことのためにできるかぎりの考える力をふりしぼりたいものである。(P.45)
第二章 人間の生きかた
神谷氏は『生きがいについて』(←Amazonの紹介ページへ飛びます)という著作が有名で、そのためか第二章はおおむね「生きがい」を軸に話を進めています。どうしたら生きがいを持ってより良い生き方ができるかという話ですが、一部の自己啓発系発信とは違って、地に足のついたいたわりがあります。こんな風に。
弱者の生命をたいせつにすることは、適者生存の法則をやぶることであるかも知れない。しかし人間はもうこの辺で、「単なる生物」の域を脱して、精神的存在としての独創性と知恵とをはたらかすべきではなかろうか。(P.75)
そして、私がこの章で特に胸を打たれたのは以下の一節です。
また自分が生きがいを感じないから、生きていても意味がない、と簡単に言えるかどうか。
かりにある人の一生が、ただ苦しみを感じるだけに終始したとしても、あるいはただ、「廃人」で終わったとしても、その人の生がかけがえのないものである、という視点もありうる。
その視点とは、「永遠の相のもとに」人間を眺めるまなざしのそれであろう。(P.67)
「どんなに苦しみだらけだったとしても、これっぽっちも生産性が無いように思えても、あなたの人生は無駄じゃないんだよ…そんな風に聞こえますね」
私もそう聞こえてなりません。この章を神谷氏は、使命ということに触れてこんな風に締めくくります。
けっきょく、私たちにできることは、何かよび声がきこえたときに、それにすぐ応じることができるように、耳をすましながら、自分を用意して行くことだけだろう。そういう人のところに、おそかれ早かれ使命が、何かのかたちをとって、現れてくる。前国連事務総長の故ハマーショルドはいう。
「使命のほうがわれわれを探しているのであって、われわれのほうが使命を探しているのではない。」(『道しるべ』みすず書房、一九六七年) (P.85)
「焦んなくていいよ、ってことかもしれませんね」
そうかもしれません。あるいは、自分が使命と思い込んでいるものが本当にその人の使命かどうかわからない、ということでもあるかもしれません。やりたい仕事と適職が時々食い違うみたいに。
ちなみに神谷氏は他の著書から拝察するに、自分が生きがい論の第一人者みたいに言われることに少し戸惑っておられたようです。
第三章 人間をとりまくもの
この章で神谷氏は罪や死など第一章で言う実存的な悩みに触れながら、人間はどんなものにとりまかれているのだろうかと考察し、最終的には「愛」の問題に言及しています。
この「良心」をもった人間は、罪の意識に悩まずにはいられない。(中略)人間に必要なのは無条件の許しと、それを素直にうけとめる「砕けた心」でしかないと思う。(P.98~99)
「いつかご紹介いただいた『罪と罰』(←本ブログの紹介ページへ飛びます)のラスコーリニコフみたいですね」
私も彼を思い出しました。罪と並んで人間にとって避けられない悩みである死について、神谷氏はこう述べます。
死の床の苦痛といっても、多くはそう長い間、意識されないものだ。愛する者との別れ、といってもほんとうは別れではなく、べつな状態で存在するだけなのだ。自分の生の意味といっても、自分にも他人にもほんとうはわからないのだ。その判断はただ人間を越えたものにまかせるほかないのだ──。(P.103)
「べつな状態で存在するだけ、と言われると少し気持ちが楽になります。私も大事な人と死別した経験がないわけではありませんので。いつかご紹介いただいた『喪の途上にて』(←本ブログの紹介ページへ飛びます)と何となく共通するものを感じます」
とても暖かい言葉ですよね。私はこれが、人類がこれまで宗教や信仰を必要としてきた、また今後も必要とするであろう理由だという気がするんです。もちろん個人としては無神論の方などもおられますが、人類全体としては、ということです。
そして「愛」の問題について神谷氏が語る言葉はこうです。
しかし、まぎれもないことは、人間がみな「愛へのかわき」を持っていることである。その大いなる実体がわからないにせよ、人間を越えたものの絶対的な愛を信じることが、このかわきをみたすのに十分であることを、昔から古今東西の多くの偉大な人や無名な人びとが証明してきた。(P.127)
人間の心の根本的な「愛へのかわき」をどうするか、という問題である。(P.130)
「人間を越えたもの、とはいわゆる神様ですか?」
特定の神や仏をあげてはいませんが、人間を越える大きな存在を想定せずに「愛」ということは考えられないと神谷氏は考えていたようです。「おわりに」でも、
以上、ずいぶんずさんではあるが、人間にみられる生命というものの特殊性、人間の生きかたのいくつかの側面、および人間をとりまく条件について考えてきた。その結果、ついに人間を越えるものを想定しないわけに行かないとし、それに支えられているものとして、生命や人間や死を考えなくては、人間は安心して生きることができないものだ、という結論に達した。(P.134)
と書いています。
結局のところ、「愛」は人間の手に負える問題ではないかもしれません。神谷氏も「人間の知恵も愛もあまりにも不純で弱い」(P.130)と述べていますしね。それでも愛そうとチャレンジし、愛とは何か考えることを多分人間はやめられませんし、それが生きるということなのかもしれません。
「『愛へのかわき』とは『愛されたい気持ち』なんだと思いますが、『愛したい気持ち』でもあってほしい気がします」
私もです。
感想
「なにわt4eさんは『人間をみつめて』を読んでどう思われましたか?」
神谷氏のどの著作にも共通することですが、学識の豊かさや人間に向ける思いの深さ、それらと相反する謙虚さには驚かされます。こんな人がいるんなら人間をもう少し信頼してもいいな、とさえ思います。
そして本書についてですが、この本は読者に、さらには人類に大きな宿題を出していると思います。
「と、おっしゃいますと?」
例えば、第一章で少し触れた「AI時代における人間の生きかた」とか第三章での「『愛』の問題」とかです。そして「おわりに」で書かれた以下の言葉は、もしかすると神谷美恵子さんが一番おっしゃりたかったことかもしれません。そして、人類が決して忘れてはならない言葉だと思うんです。
私たちは人間の小さなあたまで、ただ有用性の観点からのみ人間の存在意義を測ってはならないと思う。何が有用であるか、ということさえ、ほんとうには人間にはわからないのではなかろうか。たとえば学問でも、「人の役に立つ」とみえるもののみが価値ある、とは私は決して思っていない。(P.137~138)
「…効率と生産性が全てのような現代の潮流と正反対の言葉ですね」
ええ。静かに、しかし断固として神谷美恵子さんは天国から異議を唱えておられると思います。
【広告】ここをクリック→こちらから書籍情報をごらんください。
【広告】ここをクリック→こちらから書籍情報をごらんください。(kindle版)
【広告】ここをクリック→疲れてる、でも本は読みたい。そんな時はAmazonオーディブル。本は、聴こう。