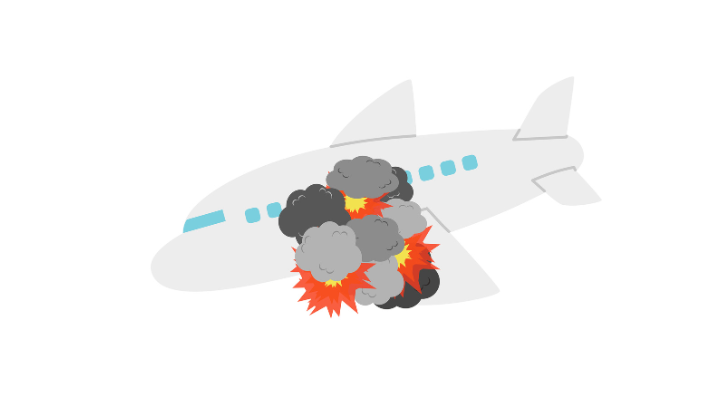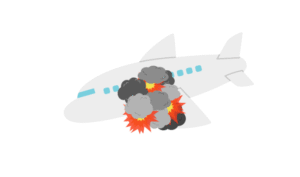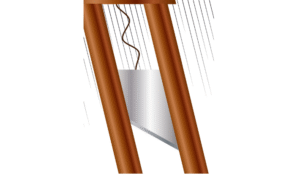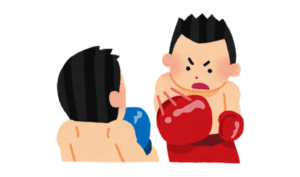先にまとめから~忘れられない航空機事故~
原爆の日や敗戦の日を除けば、あなたにとって8月の忘れられない大きな出来事って何ですか?
私にとっては12日の日本航空123便墜落事故です。私は事故の関係者ではありませんが、当時子どもだった私も(何かとんでもないことが起きた)とは感じました。そして4人の方々が生きて救助されたことは、本当に良かったことは確かです。ですが私はむしろ、(何百人も乗っていたのに4人しか助からなかったなんて、どれだけ大きな事故だったんだろう)という衝撃を受けました。そして後に述べる理由で、この事故は私にとって忘れられない出来事になったんです。
本書『墜落の夏─日航123便事故全記録』(以下、『墜落の夏』)は、日本におけるノンフィクションの第一人者・吉岡忍氏がこの事故を追い、深く掘り下げた一冊です。ただ事故の概要をたどり証言を並べただけの本ではありません。機体のメンテナンスを見学して機体内部に潜り込んだり羽田空港の周辺を歩いたり、果ては航空機のプラモデル片手に空のプロたちと議論したりと、全身全霊で事故と格闘する姿には執念すら感じます。その執念のゆえでしょう、例えば本書の第2章「三十二分間の真実」には単なる事故の再現にとどまらない背筋が凍り付く臨場感があります。また、「事故の関係者」の一言ではくくり切れない様々な想いが、胸が痛くなるほどの迫力で伝わってきます。
決して気軽に読める本ではありません。自分一人の成長を躍起になって追い求める人にも恐らく不向きな本です。ですが、大事故に厳粛な想いで向き合い、そこから社会と人間を改めて考えたいという方にはぜひお読みいただきたい一冊です。
【広告】ここをクリック→こちらから書籍情報をごらんください。
【広告】ここをクリック→こちらから書籍情報をごらんください。(kindle版)
【広告】ここをクリック→疲れてる、でも本は読みたい。そんな時はAmazonオーディブル。本は、聴こう。
美濃達夫さんとの会話
「なにわt4eさん、昨年の今頃でしたね。『喪の途上にて』(←本ブログの紹介ページへ飛びます)をご紹介いただいたのは」
そうでしたね、その本のテーマである日本航空123便墜落事故から今年(2025年)でちょうど40年になります。
「取引先の方からお聞きしたんですが、ご遺族の手記が出版されるそうですね」
あ、私もそれニュースで知りました。本屋さんの店頭に並んだらぜひ読みたいです。
「あれだけの大事故だと、やっぱり関連書籍も多いでしょう」
ええ。実はこの事故に関して、つい先日読んだ本をぜひご紹介したいんですよ。
「何と言う本ですか?」
吉岡忍『墜落の夏』です。
「ぜひ紹介したいとおっしゃいましたが、それはどうしてですか?」
理由は3つあります。
- 事故の真実を掘り起こす吉岡氏の執念に引き込まれたから。
- 生きている方・亡くなった方、どちらに対しても一人一人に最大限の敬意を払う吉岡氏の姿勢を見て「この本は信頼できる」と感じたから。
- かつて『喪の途上にて』を読んだ時、著者の野田氏がご遺族の一人一人に真摯に向き合う姿勢に触れてそれが強く心に響いたこと、その影響もあってこの事故が私にとって忘れられない事故になったから。
「そうお聞きして私も大変興味を引かれます、ぜひお聞かせください」
事故の概要
事故の概要は『喪の途上にて』と当然ながら同じですが、『墜落の夏』では異常発生から墜落までの約32分が非常に詳しく記録されています。
「どんな風にですか?」
生存者の1人である落合由美さんの証言やボイスレコーダー、亡くなった方が機内で残したメモなどに基づいて詳しく、かつ分かりやすく書かれています。あまり長々と引用するのは控えますが、この記述だけで怖ろしさの一端は伝わるんじゃないでしょうか。
「ハイドロ全部だめ」という叫びは、操作によって上下左右に動けるという信頼感にもとづいて空中を飛んでいる航空機が、いっさいの操作を受けつけないただの金属の空洞と化して、ひたすら前方へ突進している事態に入りこんでいる、ということであった。これはもう、飛行機などと呼べる代物ではなかった。(P.87)
「ハイドロ全部だめ」というのは要するに、パイロットがいくら操作しても機体にそれが伝わらない状態ということです。
「…そうお聞きしただけでゾッとします」
またこの事故は一般的に、過去の修理ミスから金属疲労によって隔壁破壊が起きたことが原因とされています。吉岡氏は、これを覆そうとするわけではないですが丸暗記のように飲み込むことに疑問を抱き、無数の資料や証言、インタビューに基づいて調査しています。私はここに吉岡氏の執念を感じました。
だが、JA8119号機(引用者注:事故を起こした機体の識別番号)の墜落事故は、ほんとうにそれだけを理解すればいいことなのだろうか。日航ジャンボ機事故、すなわち隔壁問題、とまるで暗記試験問題を片付けるようなことでいいのだろうか、と私は感じていた。そこには、巨大技術と人間との関係をめぐっても、巨大事故の犠牲者の身元判明の手法に関係しても、あるいは複雑なテクノロジーと保険制度を組込んだ現代社会のリスクとその分散についても、深く考えなければならない問題がふくまれているように思われた。(P.61~62)
事実、吉岡氏の考察は保険制度や社会全体の構造にまで及んでいます。
吉岡氏が記録した人間像
これは一言で要約すべきことでもできることでもないと思うので、強く心を打たれた記述をいくつかピックアップします。
その冷静なはずの男たちが、突然、泣きそうになったり、あわててライフ・ベストをふくらませてしまったりしたというのだった。(中略)あの日の機内には、女性もたくさんいた。(中略)しかし、彼女たちの方が落着いて、気丈だったという。ライフ・ベストをふくらませてしまった女性の乗客もいなかった。(P.151~152)
しかし、激しく揺れる機内では、あわて、おびえ、泣きだしそうになって、すぐにふくらませてしまう男たちが少なくなかった。彼女の話のあとで座席番号と乗客氏名を照合してみると、いずれも一流と言われる有名企業に勤務するビジネスマンたちであった。私だって、その場になったら、やりかねない。
だが、K氏は冷静だった。彼は、スチュワーデスや落合さんと一緒になって、機内ではふくらまさないように、と叫んだという。(中略)冷静なだけではない品位を、私は感じた。(中略)一人ひとりの実質がむきだしにされるときも、輝くものを失わない人がいる。三十二分の機内には、そうした輝きの場面がいくつかあったにちがいない。(P.158~159)
「いざとなると男は頼りなくて女はしっかりしてる、というのはよく聞く話ですね。私もその場にいたらどうなっているやら」
大事故の現場だけに美談扱いをするのはためらわれますが、「一人ひとりの実質がむきだしにされるときも、輝くものを失わない人」にはどうすればなれるのかとは時々考えます。そして、ビジネスの現場も戦いであることは確かですが、歴戦の勇士であるはずのビジネスマンがこのありさまで女性が沈着・気丈であるなら、本当の戦いとは何だろうかとも。
その直前、親戚のひとりが東京の日航本社に電話を入れている。「すぐ社長をよこせっ。あの事故の遺族が死にそうなんだ。事故さえなければ、こんなことにはならなかった。遺族の苦しみがどんなものか、よく見ておいてほしい」と。日航からは、しかし、だれも来なかった。通夜に高木養根元社長がきたとき、集まっていた遺族らが、「死んでからきて、どうなる。苦しんでいるところをこそ見てほしかったのだ」とつめよる場面があった。(P.181、ふりがなは原文のまま)
「…『社長にだって都合がある、言われたからってそうそう必ず行けるものか』と言うこともできるでしょうけど、ご遺族からすれば『遺族のいのち以上に大事な都合があるのか、ましてやお前の会社の事故だろうが』というお気持ちなんでしょうね」
外野の想像に過ぎませんが、そうだと思います。 ところでそのご遺族の集まりですが、「8.12連絡会」と名付けられています。この点について吉岡氏はこう述べています。
遺族会、としなかったことに、彼らの強い意志が感じられた。夫や妻や子供を失っても、自分たちは、同情の対象にされる、弱々しい、受身の存在ではなく、以後の生活を自分で切り開いていく、積極的な生の当事者なのだ、という決意が、その名称にはこめられていた。(P.286~287)
「そう言えば『喪の途上にて』をご紹介いただいたときも、原因究明のために活動しておられる川北宇夫(たかお)さんというご遺族のお話しがありましたね」
そうでしたね、覚えてくださっててありがとうございます。8.12連絡会の方々と川北さんには、意志力のようなものを共通して感じました。
こうして見ると吉岡氏は人間の浅ましさや頼りなさ、硬直してしまったような心のあり方を直視する一方で、それでも人間を信頼しよう、敬意を払い続けようとしておられるように思えます。
吉岡氏が見ようとしたもの、書こうとしたもの
この本は日本航空123便墜落事故のとても緻密なルポルタージュであると同時に、人間の本質や日本社会のあり方に対する考察でもあると私は思うんですよ。
「と、おっしゃいますと?」
例えば、ご遺体の安置所となった体育館でのエピソードです。季節のせいもあってたちどころに無数の大きなウジがわいたんですが、こんなことを言った人がいるそうです。
「あんなので釣りをやったら、魚はぴんぴんかかってくるだろうな」、そんな冗談で気味の悪さを払おうとした医師もいた。(P.214)
美濃さんはこの言葉をどう思われますか?
「不謹慎な冗談だとは思いますが、そうとでも言わなければやっていられないくらいきつかったんでしょうね、肉体的にも精神的にも」
私もそう思います。吉岡氏もこの言葉を、擁護していない代わりに非難もしていません。また、乗客が機内で残した遺書やメモに触れて、吉岡氏はこう書いています。
<ビッグ・ビジネス・シャトル>のなかでは、乗客のだれも仕事のことを書き残さなかった。(中略)いきなり死に直面したとき、乗客たちがとっさに書いた文章の内容は、死にたくない、というぎりぎりの言葉と、家族にあてた愛と惜別の言葉だった。それしか、なかった。(中略)遺書に残された言葉は、その背後で、新しさや、先端にあることや、競争に夢中になることの、あやうさと儚さを語っているように、私には感じられた。そんなものをきどるよりも、ずっと大切なことがある、と。(P.187)
そしてこう続けています。
もちろん、それは、だれもが自覚しているにちがいない。競争に追われ、小さな勝利に満足し、ささいな敗北にがっかりする、そんな日常のくり返しのうさんくささは、だれもが気づいている。しかし、気づいていながら、表層を飾り、きどってふるまい、関係のなかの孤独を耐えることのほかに、どんな日々の暮らし方があるのか?(P.187~188)
「家族、あるいは他の誰かを大切に思いながらも、小さな世界の生存競争に躍起にならざるを得ない…私たち自身も同じですね」
誰かがその生存競争に躍起になって働いてくれているおかげで自分は家族を愛することができる、そしてその誰かと自分を入れ替えても同じこと、せめて最後の瞬間には家族なり誰なり、大切な人の顔が思い浮かぶような生き方を模索しなければならない…今のところ、私はそう考えています。
そして日本社会、というより現代社会について末尾でこんな考察がなされています。人間は一人一人違うものだし、個性的であるべきだと言われる一方で、そのような個性が社会のシステムの中で求められることはない、と。(P.346)
「それは否定できませんね。この歯車はこの速度で回るとか、このネジの耐久性はこれくらいだとか、そうしたことが均一じゃないと機械は安全に動かないわけですから。社会も同じことが言えますし」
ええ。吉岡氏は「人間の均質化に向かって、私たちは歩いてきたし、これからもその軌道をはずれることはないにちがいない。(P.346)」と述べ、本文をこう結びます。
信頼で結ばれる大小無数のシステム世界の裏側を、じわじわと侵蝕していくものの存在を私は感じとった。その存在こそが精密で巨大なシステム体系を形成する動機ともなれば、エネルギーともなるもの──人間に対する不信を、である。(P.347~348)
「そこだけお聞きすると分かりにくいですが、あまり楽観的な結論ではなさそうですね」
私もそんな気がしています。人間を信頼し、かつ社会のシステムをスムーズに動かす方法や考え方が、もしかすると現代には求められているのかもしれません。
感想
「大変情報量が多くて中身の濃い本みたいですが、なにわt4eさんはどう思われましたか?」
繰り返しになりますが、事故を見つめることを通じて吉岡氏は人間の本質や社会のあり方を見つめているように思います。そのまなざしの真摯さに、と言うより執念深さに、引き込まれるように読みました。
題材が同じ事故だから当然ではありますが、『喪の途上にて』と同じエピソードがいくつも書かれている点も興味深かったです。
「例えば、どんなエピソードですか?」
墜落現場の土をご遺族に売ろうとした者がいたこと(『墜落の夏』P.227~229、『喪の途上にて』P.384)、遺体の置き場となった体育館にマスコミの取材攻勢を防ぐためあらゆる窓に黒い幕が張られたこと(『墜落の夏』P.204、『喪の途上にて』P.23)、当時の高木社長の人間性が硬直したようなあり方(『墜落の夏』P.181、『喪の途上にて』P.32、P.286)。確認できてないんですが、検視にあたって内科と外科それぞれの医師を一組にしたという記述も(『墜落の夏』P.207)共通している気がします。
なおこの事故については、やれ米軍機が追尾していたとか自衛隊機が演習で123便を狙っていて誤射したとか、様々な陰謀論や憶測が出回っています。ちょっと興味を持ったにすぎない素人の私でも、これには腹立たしい思いをしています。こんな面白半分の憶測は、犠牲者やご遺族始め、関係者に対する冒涜以外の何物でもありません。そんな暇があったら、それこそ吉岡氏の本でも読めと言いたいです。
●『墜落の夏』に興味を持たれた方は、以下の本もどうぞ。(全てAmazonの紹介ページへ飛びます)
・髙村薫『レディ・ジョーカー』
人間性が硬直してしまったような高木社長(事故当時)のあり方に、私は日之出ビールの城山社長を連想しました。『墜落の夏』第3章で描かれる空港周辺の風景も、『レディ・ジョーカー』の半田が住んでいるあたりと似ている気がしておもしろかったです。
・塩田武士『踊りつかれて』
「炎上」をテーマとした、本記事執筆時点での塩田氏の最新作。『墜落の夏』で吉岡氏が自戒を込めて触れているマスコミの取材攻勢は、『踊りつかれて』で主要キャラクターを苦しめるマスコミやSNSユーザーとそっくりでした。
・野田正彰『喪の途上にて』
本文で何度も触れましたが、精神科医の視点という異なる角度から書かれているので、両方を読む意味はとても大きいです。
【広告】ここをクリック→こちらから書籍情報をごらんください。
【広告】ここをクリック→こちらから書籍情報をごらんください。(kindle版)
【広告】ここをクリック→疲れてる、でも本は読みたい。そんな時はAmazonオーディブル。本は、聴こう。