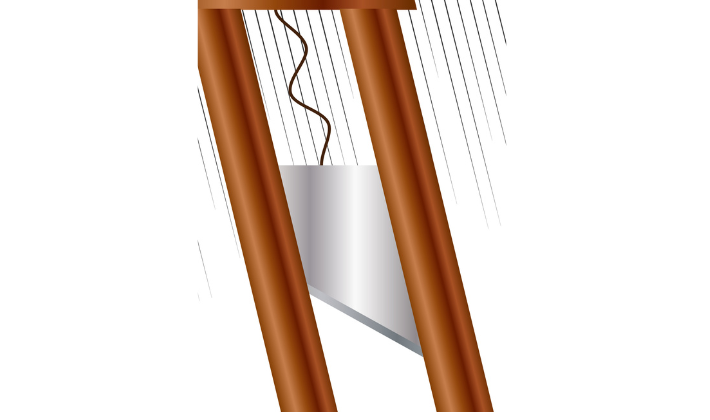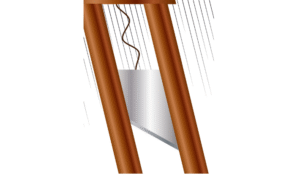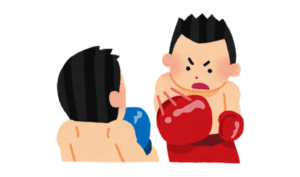先にまとめから~ネットありきの現代だから読んでいただきたい歴史ロマン~
繰り返される炎上・ネットリンチ・匿名の断罪──これらは今に始まったことでしょうか? インターネット以前にも魔女狩りや赤狩り、関東大震災の自警団など「正義の名のもとに他人も自分も地獄に叩き落とした」例は枚挙にいとまがありません。
アナトール・フランス『神々は渇く』は、そんな「正義の暴走」を革命当時のフランスという舞台で描く作品です。吹き荒れる「正義」は人間をどう狂わせるのか? どうすればそれを防げるのか?
もちろんそれだけの作品じゃありません。人生の楽しみ方をよく知るナイスおやじ、子ども同士の対立に心を痛める優しい母親、誇り高く死んでいく弱者──本作はそんな彼らの人間らしさが躍動する、迫力満点の人間群像でもあります。
フランス革命の知識がない人(私もそうです)にはピンときにくい箇所もあります。でもだいじょうぶ! 狂信が招く悲劇と個性豊かなキャラクターを描く本作はネットありきの現代を生きる私たちにとって、他人事とは思えない一冊です。
こんな方には特におすすめします。
・ネットリンチや〇〇叩きに違和感がある方
・皮肉や警句が好きな方
・世論って何だか気まぐれじゃない? と思う方
【広告】ここをクリック→こちらから書籍情報をごらんください。
【広告】ここをクリック→疲れてる、でも本は読みたい。そんな時はAmazonオーディブル。本は、聴こう。
美濃達夫さんとの会話
(架空の人物・美濃達夫さんに本書をご紹介する、という設定で書いております)
「なにわt4eさん、最近また飲食店でのイタズラが炎上してましたね」
ああ、ありましたね。もちろん行為自体は重大な営業妨害ですし、許される行為ではありませんが、それを晒して楽しむというのはまた別の大きな問題行為だと思います。
「そっちもそっちで犯罪にあたる可能性がありますしね。それこそ、先日ご紹介いただいた『踊りつかれて』(←本ブログの紹介ページへ飛びます)を思い出します」
私もあの本を思い出しました。
「あの時、関連書籍をいくつかご紹介くださってましたね。ええと、『神々は』なんでしたっけ?」
『神々は渇く』ですね。実はこれも私の大好きな本なんですよ。
「気になります。どんな本ですか?」
あらすじ
舞台は革命の熱も冷めた頃のフランスです。深刻な貧困や食料不足がパリに蔓延し、若い画家エヴァリスト・ガムランと彼の母親は今日のパンにも事欠く生活でした。そんな中でもエヴァリストは新手のトランプを考案したり、元貴族の隣人モリース・ブロトは人形作りをしたり、苦しいなりに生計を立てていました。
エヴァリストは画商の娘エロディと恋仲になり、また革命裁判所の陪審員に任命されます。名誉ある職であり金銭的にも多少は恵まれる立場でもあり、何よりフランス革命の理想に燃え続けるエヴァリストにとっては夢のような仕事でした。しかし革命裁判所はもはや、革命を狂信する人間の巣窟でした。初めは戸惑いを感じたエヴァリストもほどなくそれに染まり、しまいには「こいつはかつてエロディを誘惑した」と思い込んでエロディとも反革命とも無関係な人物ジャック・モベルに死刑判決を下すありさま。
ある日パンを買う行列に並んでいたエヴァリストとブロトは反革命の容疑で追われていた神父ロングマールと知り合い、後日ブロトはロングマールをかくまいます。ブロトは若い娼婦アテナイスとも知り合いました。「娼婦は反革命である」という理由で追われて逃亡中だった彼女にブロトは自分の叔母を紹介します。
エヴァリストの妹ジュリが、母親の元を訪れました。彼女は貴族にして亡命者サシャーニュとイギリスに駆け落ちしており、兄とは対立していました。サシャーニュが反革命容疑で逮捕され、彼を救うべく危険を冒してフランスへ戻っていたのです。
やがてブロト、ロングマール、アテナイスは逮捕され革命裁判にかけられます。そしてエヴァリストは……。
魅力いっぱいの登場人物
今回も登場人物のご紹介に重点を置いてお話ししましょう、単に狂信をいさめるだけの物語じゃありませんので。
エヴァリスト・ガムラン:優しき貧乏画家、後に革命裁判所の陪審員に
彼が基本的には主人公です。母親と二人暮らし、妹がいますが彼女の駆け落ちで袂を分かっています。
「フランス革命って『貴族はくたばれ』ですから貴族と駆け落ちした妹と対立するのはまあ分かるんですが、完全に縁を切っていたんですか?」
恐らく。それくらい革命に熱狂してましたが、ジュリが隠れていることに気づいていながら気づいてないふりをしたり(岩波文庫、以下同じ、P.262)自分自身が空腹すぎて赤ちゃんに母乳もやれない見ず知らずの女性に自分のパンを譲ったり(P.94)という人間らしさも残っていました。そして彼は自分がいかに異常な人間になってしまったか自覚しています。
「どういうことですか?」
反革命の手先を何人もギロチン送りにした自分がこれ以上君と一緒にいるわけにはいかない、と言ってエロディに別れを告げるんです。ここで、自分とぶつかった通りすがりの男の子を抱き上げた後でエロディにこう話します。
僕はあの少年を抱いた。ひょっとするとあの子の母をギロチンにかけさせることになるかも知れない。(P.319)
「……文の内容も恐ろしいですが、この短い文章でエヴァリストの二面性を表現する作者の文章力にも驚きました」
でしょう?
ガムラン夫人:兄妹の対立に心を痛める母親
「しかし子ども二人がそれじゃ、母親も気が気じゃないでしょう」
ええ、ガムラン夫人(名前は出て来ません)は気をもみ通しで、革命にも懐疑的です。
人間は決して平等になることはあるまいからね。それはありえないことだよ、どんなに国をひっくり返してみたところで、お偉方とささやかな庶民と、太った者と痩せた者とがあることには変りはないだろう。(P.30~31)
「今のところは母親の方が正しいような……」
少なくとも現状はそうですよね。とは言えエヴァリストが革命裁判所の陪審員になると、正義感の強いお前にはぴったりだ、鼻が高いと大喜び。そこが妹ジュリと対立する原因でもあったんですが。ジュリがサシャーニュを救うため帰宅した時は、ガムラン夫人はジュリとエヴァリストの鉢合わせを恐れてオロオロしています。
「仲が悪い兄弟にやきもきする母親、というのはよくある話ですね」
とは言え、エヴァリストの足音を聞きつけるととっさにジュリを自室に隠れさせ、サシャーニュの助命を頼もうとする行動力や芯の強さもあります。
ジュリ・ガムラン:貴族と駆け落ちして兄と対立する妹
「で、貴族と駆け落ちしたということは、母親のみならずジュリも革命に懐疑的だったということですか?」
どうでしょう、もしかすると革命に興味が無かっただけかもしれません。ただ兄への強い反発と、母親が兄ばかりをかわいがるという疎外感を強く抱いてました。
わかったわ、お母さんは兄がどんな人間かってことを今では知っているのね。冷酷非情で、意地悪で、野心と虚栄心しか持たない人間だってことを知っているのね。だのにお母さんはいつも兄を私よりも可愛がって来たのね。(中略)お母さんは兄だけしか愛していなかったのね。いっておくけれど、わたし大嫌いよ、お母さんのエヴァリストなんか。あれは偽善者よ。(P.254)
兄は善行はできない人なのよ。(中略)あの人が誰かを愛せると思って?(P.255)
「なかなかボロカスですが、複雑な思いがありそうですね」
ええ。率直で活発な自分は愛されなかったという思いがジュリにはありますが、ある点は兄エヴァリストと似ているかもしれません。
「どんな点ですか?」
行動力です。この時代にフランスからイギリスへ駆け落ちした点もそうですし、シャサーニュのために危険を冒してパリに戻った点、そして助命を乞うべく判事ルノダンに会いに行った点にそれを感じました。エヴァリストも革命裁判所の陪審員として積極的に活動していましたしね、やってることの是非はともかく。
「対立しながらもどこか似ている、やっぱり兄妹なんですね……だから難しいんでしょうけど」
モリース・ブロト:人生に精通した哲人にしてナイスおやじ
彼は第二の、あるいは真の主人公かもしれません。
「どういうことですか?」
エヴァリストやロングマールと丁々発止の議論をし、と言って敵対もせず良き隣人として敬意を払い、ロングマールやアテナイスを助けるという大活躍だからです。彼は死の間際まで人生を愛し続けます。
「おもしろそうな人物ですね」
そりゃもう。革命のため凋落してますが、ローマの詩人・哲学者ルクレティウスを愛し、無神論哲学を縦横に展開するインテリです。
「無神論哲学?」
ええ、ブロトはロングマールにこう言っています。哲学者エピクロスの言葉だそうで、長いので私なりに要約すれば……。(P.209)
──神は悪を止めたいのにできないのか。だとしたら神は無能です。神は悪を止められるのにその気がないのか。だとしたら神は邪悪です。神は悪を止めることができないしその気もないのか。だとしたら神は無能で邪悪です。神は悪を止めたいしそれができるのか。だとしたら神はなぜそうしないのでしょう?──
「その言葉をどう考えるかはともかく、論理の進め方がいかにも西洋哲学っぽいですね」
そうですよね。かと思うと
しかし猫たちが恋のために屋根の上でにゃあにゃあ泣いたりいがみ合ったりするぐらいのことは赦してやらなくてはなりませんな、恋は人間の生活を苦悩と犯罪とで満たしていることを思えば。(P.162)
と言ってのけるユーモアもあります。
「ははは、大したナイスおやじじゃないですか」
ブロトは挙げればきりがないくらいの名言製造機ですよ。かと思うと自分も貧乏暮らしでありながらロングマールやアテナイスに力を貸す情の厚さがあり、恩には着せない。ロングマールから感謝を述べられた時はこう言っています。
わたしは利己主義からしているのです。人間にあらゆる健気な行為や献身的な行為をさせるあの利己主義、われわれをしてすべての惨めな人々の裡にわれわれ自身の姿を認めさせる利己主義、他人の不運を憐れむことによって自分自身の不運を憐れむ気にわれわれをならせる利己主義、生まれつきと運命との点で自分に似た人間を助けよとわれわれをそそのかし、ついにはその人間を助けることが自分自身を助けることであるとわれわれに思いこませるに至る利己主義、──あの利己主義から、わたしはしているのです。(P.185)
「ちょっとカッコつけっぽい気もしますが、『共感や助け合いなしには人間は生きていけないからですよ』と聞こえます」
そう聞こえますよね? 最後は反革命の容疑で有罪判決を受けるのですが、終始落ち着いています。「酸いも甘いも嚙み分けた」とは彼のためにあるような言葉です。
アテナイス:誇り高く処刑される年若い娼婦
彼女は16歳ですが貧困のために体を売っています。「娼婦=反革命」という理由で追われている時にブロトに出会い、ブロトの叔母を保護者として紹介されました。それ以来彼女はブロトを命の恩人として慕い、お礼として卵とパンケーキをブロトに差し入れしようとしました。
「作中ではパンすらなかなか買えなかったんですよね? 卵やパンケーキってかなりの貴重品だったのでは?」
だと思います。ですが、彼女が来た時ちょうどブロトは反革命の容疑で逮捕されるところでした。彼女は抗議します。
──この方を連行するのではないでしょうね? そんなことってないわ。……あなた方はこの方を御存知ないのよ! 神様のようにいい方なのに。(中略)それから、ティヨンヴィル広場全体にひびき渡り、野次馬の群をふるえ上がらせるような声で、彼女は叫んだ。
──国王万歳! 国王万歳!(P.248)
「『国王万歳!』は反革命を象徴する言葉なんでしょうが、アテナイスは革命に反対だったんですか?」
というより、無実の恩人が逮捕されることに怒ってこう叫んだのでしょう。終盤、処刑場に連行される場面です。
彼女は身も軽やかに、二輪荷馬車の上に乗った。そしてそこで、胸を真直ぐに起こし、その子供のような顔を誇らかに上げて、叫んだ。
──国王万歳!(P.310)
アテナイスは、フランスの王妃と同じようにして死ぬことを誇りに思って、高慢なまなざしを群集の上に投げていた。(P.311)
彼女は「革命への狂信」という怪物に誇り高く抗議を突きつけました。彼女もジュリ同様、出番は少ないがカッコいい女性だと思います。
移り気な「正義」──「炎上」「ネットリンチ」に通じるもの
「そう言えば先ほど、舞台は革命の熱がすっかり冷めたフランスとおっしゃってましたね」
ええ。本作は「『正義』の移ろいやすさ」も重要なテーマです。物語序盤でマラやロベスピエールと言う人物、彼らはフランス革命三巨頭の二人と呼ばれているそうで、革命の神さながらにあがめられています。しかしエヴァリストが処刑される頃になると市民から蛇蝎のごとく嫌われています。
例えばマラは「感じやすい、人間的な恵み深い人」「決して謬り(引用者注:「あやまり」、原文のまま)を犯したことがなく、すべてを見抜き、すべてをあばく勇気があったあの人」(P.108~109)と尊敬されてましたが、終盤には「マラをやっつけろ!」「毒蝦蟇!」「虎!」「黒蛇!」(P.348)と言われる始末。しかもとっくに暗殺されていたのに。
「詳しい背景は分かりませんが、ずいぶんな手のひら返しですね」
ええ。ブロトも
わたしたちはあまりにも見て来たからね、君たちが祭り上げたかと思うと手のひらを返すように突き落とした偉大な市民たちを。(P.48)
と端的に言っています。
だからこそ、どんな美徳や正義であってものめり込んではいけないとアナトール・フランスは言っているのではないでしょうか。私が『踊りつかれて』(←本ブログの紹介ページへ飛びます)をご紹介した時に関連書籍として本書に触れたのは、『神々は渇く』をインターネットの世界に置き換えればそのまま『踊りつかれて』の世界だと思うからです。
感想
「ずいぶん思い入れのある本みたいですが、なにわt4eさんのご感想をお聞かせください」
非常に重い本と思われたかもしれませんが、けっこうユーモラスな面もあります。例えばブロトが人形について「わたしはこれらの被造物に思考力は与えなかった。というのもわたしは恵み深い神だからです」(P.18)と言ったり、エヴァリストも自分の貧乏暮らしを「何のために閂(引用者注:かんぬき)をかけるのです? 蜘蛛の巣を盗む者はいませんよ」(P.20)と笑い飛ばしたり、ブロトから食事に招かれてロングマールが遠慮していると「決して山海の珍味をお出しするわけではありませんよ」(P.202)と言われてやっと承諾したり。
「ははは、ちょっと皮肉っぽいですね」
ええ、そのおかげで気張らずに読めます。何より、本書を読むたびに思うのは
1.正義の暴走はどうすれば防げるのか?
2.逆に、正義の暴走を避けつつ虚無主義や冷笑主義をも避けるにはどうすればいいか?
ということです。
「まず2.についてですが、何か決して見過ごせない問題を訴えた時に『それって正義の暴走じゃん』と嘲笑するような言動のことですか?」
ええ、まさしくそれです。いじめとかハラスメント、差別など「人間の尊厳を踏みにじる行為」については「正義の暴走を避ける」という名目で黙っていることは許されません。
かと言って、今度は1.の方ですが、だったらそれらと戦うためなら何をしても許されるかと言ったら、それも違うと思います。でないと、それこそ『踊りつかれて』で描かれたような晒しを正当化することになりますから。
「では何が必要だと思われますか?」
実のところ、私も結論を出すには至ってません。ただ今のところは、共感とユーモアは絶対必要だと考えてます。笑う人がいたら一緒に笑い、泣く人がいたら一緒に泣く心。厳しい現実をちゃんと認識しつつも時には笑い飛ばすユーモア。最低限これらが求められると思います。そのどちらも豊かに持っていたのが、モリース・ブロトでした。岩波文庫の表紙にはこうあります。
人間は徳の名において正義を行使するには余りにも不完全だから人生の掟は寛容と仁慈でなければならない、として狂信を排したアナトール・フランス
ネットありきの社会に生きる私たちが本書から、とりわけブロトから学ぶべきことはいくらでもあります。だからこそ、今こそ読んでいただきたい一冊です。
●『神々は渇く』に関心を持たれた方は、こちらの本もどうぞ。(全てAmazonの紹介ページへ飛びます)
・『白鯨』ハーマン・メルヴィル
ジョークや警句と言ったらこれは外せません。人間なんざ笑い飛ばせ!
・『トリストラム・シャンディ』ロレンス・スターン
文学史上もっとも読者をおちょくり倒した小説。ゆる~いユーモア連発の中に寛容さと思いやりの重要性が浮かび上がります。
・『踊りつかれて』塩田武士
本文中でも何度か触れましたが、炎上やネットリンチを通じて希望を捨てない人間の強さを描く名作です。
【広告】ここをクリック→こちらから書籍情報をごらんください。
【広告】ここをクリック→疲れてる、でも本は読みたい。そんな時はAmazonオーディブル。本は、聴こう。